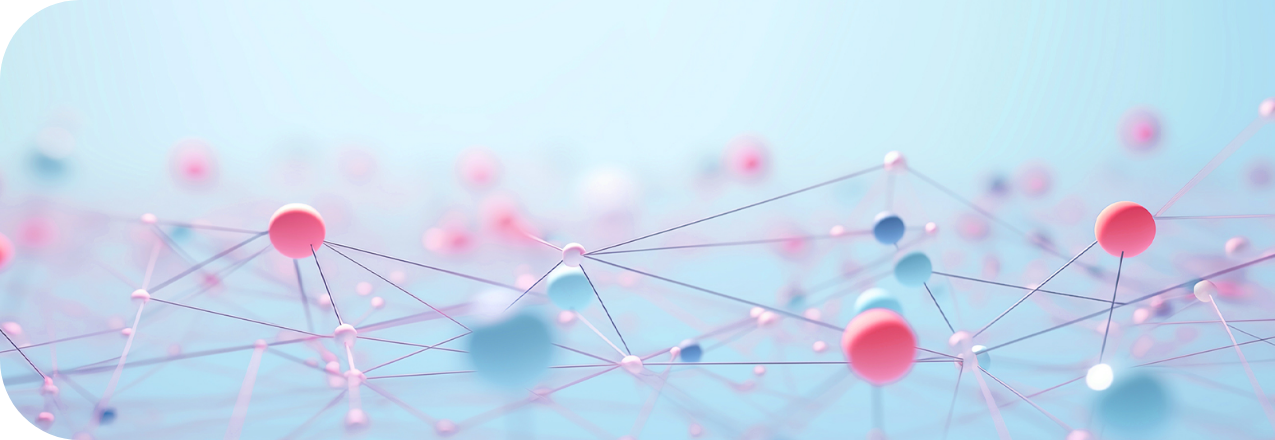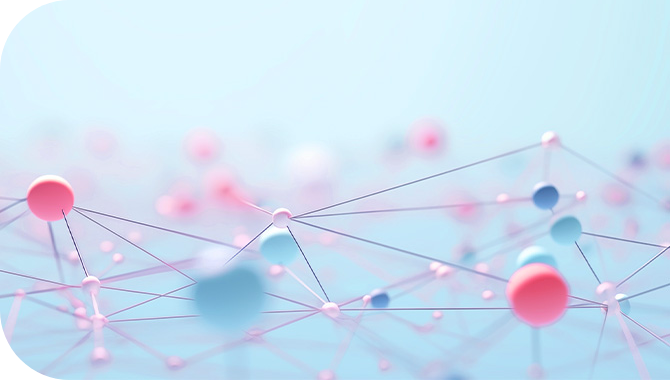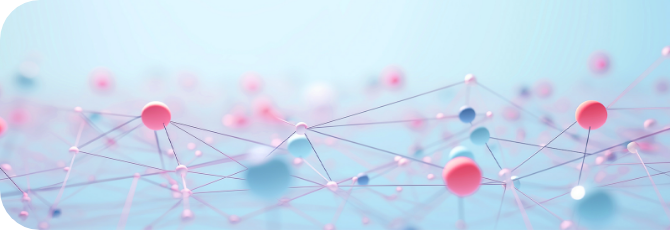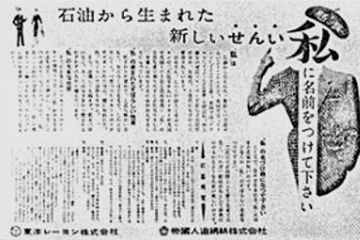20世紀中頃、日本経済は戦前水準へ回復し、かつて無い高度経済成長期の最中。同時にそれは技術革新と消費革命の新しい時代の幕開けでもあった。もちろん繊維業界も例外ではなく、ヤギの事業も時代と共にさまざまな方向へと進化を遂げる。時勢と共に変わりゆく社会のニーズに歩みを合わせるように、「原料」「テキスタイル」「二次製品」の3分野を新たに展開。いずれもヤギを支える事業の柱として、その後大きく成長していくこととなる。
1951年、新たな繊維としてナイロンが市場に出された。ヤギはいち早く先発企業であった東洋レーヨンに掛け合い、グライダーの牽引ロープを開発。次いで、被服用テープ、ストッキング用のナイロン糸、消防用のホースなど、新たな繊維を活かした商品を続々と世の中に送り出す。アクリル系繊維の登場とともに、合成繊維の取り扱いは増加の一路を辿り、1958年には正式に合成繊維部を発足。化粧用パフをナイロンに置き替えることに成功し、ナイロン素材の新しい用途を開発したとして業界からの注目を集めた。
合成繊維部の発足から4年後の1962年には、テキスタイル部門への進出を試みる。これまで肌着用として限定されていた編物が、合成繊維の進出と編機の発達によって新たな外衣用生地として脚光を浴びるようになっていたことを受けて、ニット生地の販売を目的とした編物部を発足。これがヤギのテキスタイル部門の始まりである。現在ではニット生地のカラーリスクを自社で負い、在庫販売する「テキスタイル・プロジェクト」を積極的に推進。中・大手アパレルメーカーの多様なニーズに応えている。
1960年代は経済成長のなかで国民の消費生活が大きく変化した時代であった。衣料消費も増大へと向かう中、1961年、内地織物部に製品課が新設される。その目的は原料、素材から“川下”、いわゆるアパレル事業への拡大であった。製品を扱う上では、消費者ニーズの変化に合わせた多様化、さらにはファッション化への迅速な対応が求められる一方で、量産、量販による実用衣料のコストダウンを図ることも必要不可欠。製品課を設けることで東南アジア、韓国、中国からの二次製品輸入を拡大させていった。時代が平成に変わる頃、ヤギはこの川下への志向をさらに強化する。1992年にはファッション事業開発室を新設し、原糸や生地の大量取り扱い型営業から高付加価値商品をタイムリーに企画、生産、供給できる体制を整備。専門的なノウハウの蓄積と洗練されたデザインスタッフを両立させることで、独自性と消費者により近いスタイルを生み出していく現在のビジネススタイルを確立していった。

- 拡大
- 二次製品輸入に向けた香港展示会